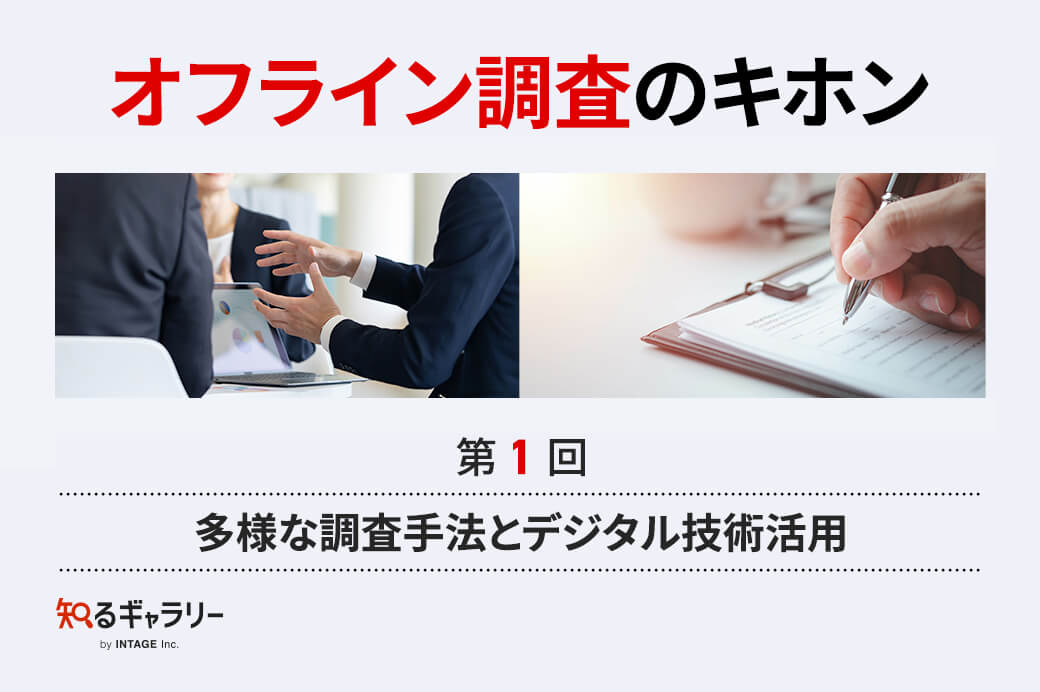

近年ふたたび社会実装の動きが加速しつつある「メタバース」。「メタバースとマーケティングリサーチ【前編】~メタバースの現状と、マーケティングへの活用可能性」では、メタバースの定義や概要、マーケティング分野での代表的な活用事例をご紹介しました。また、メタバースをマーケティングで活用するためには、体験価値の設計と効果測定をワンセットで考えることが重要という点についても紹介しました。
後編では、その点も踏まえ、インテージグループが取り組んだメタバース内での研究の事例と、そこから得られた知見を簡単にご紹介します。
メタバースがマーケティングリサーチ手法にもたらす利点としては、以下のようなものが考えられます。インテージグループ各社では、この特性をマーケティングリサーチマーケティングリサーチに応用し、その高度化に向けた実証研究を重ねています。
この記事では、メタバースのこれらの特性を踏まえつつ行った取り組みを3例ご紹介します。
株式会社インテージでは、2023年3月に開催されたメタバースでの大型フェスティバル「SBI Neo festival NEXUM 2023 (YouTube動画) 」(※ご注意※音が流れます)に協力。メタバース来場者の行動ログとアンケート調査を組み合わせた分析を行いました。
「SBI Neo festival NEXUM 2023」では、eスポーツとアーバンスポーツの複合大会を中心に、多種多様な展示やメタバース来場者間のコミュニケーションが行われました。来場者による「観戦」「移動」「SNS投稿やシェア」などの行動ログをとメタバース内で実施するアンケート結果を紐づけることで、「来場者の行動とイベントの満足度」や「来場者の行動とブランドの評価」の相関性などを検証しました。
その結果、以下のような傾向が明らかになりました。
まず、映像を中心とした視覚的に訴求力の高いコンテンツを多く取り入れたゾーンほど来場者の滞在時間が長く、それに伴ってイベント全体の満足度が向上する傾向が明らかになりました。
また、会場中央に設けた共有スペースを経由して各エリアへアクセスする動線を採用したことで、参加者が自然に会場内を巡りやすくなり、結果として各ブースの訪問率が底上げされることが確認できました。
一方で、一部コンテンツでは想定より離脱率が高かったため、導線や体験内容、インセンティブの再設計に向けた課題が示唆されました。
なお、このようなメタバース空間で来場者の行動を分析するには大量のログデータが必要です。特に、性別・年代などの属性ごとに精緻な分析を行うためには、より大量のデータ収集が必要といえます。
しかし、メタバース空間でのログデータ収集時は、通信遅延などによりデータが欠ける可能性があります。これを防ぐためにも、今後より詳細な分析を行うためには、大量かつ高精度なデータ収集を安定して行う仕組みが必要になると思われます。

株式会社インテージヘルスケアでは、30~40歳代のがん患者を対象に、メタバースを活用した座談会を開催しました。「自身の姿を他者に見せたくない」「プライベートな話題は話しにくい」などの不安が参加者にある場合の新たなインタビューの手法として、有用性を確認しました。
座談会は2回に分けて実施しました。また、対象者はVRヘッドセットを付けずにPCにログインし、「画面上のアバターをキーボードとマウスで操作する形式」で座談会に参加しました。
各回にはさまざまながん種の患者3~4人が集まり、モデレーター(進行役)が提示したテーマを中心に意見を出し、感想を話しました。テーマは「あなたにとって心地よいオンライン上のつながりとは」「がんになって自分自身が勘違いしていたと思うこと、周囲の勘違いや偏見を感じることはあるか」などです。
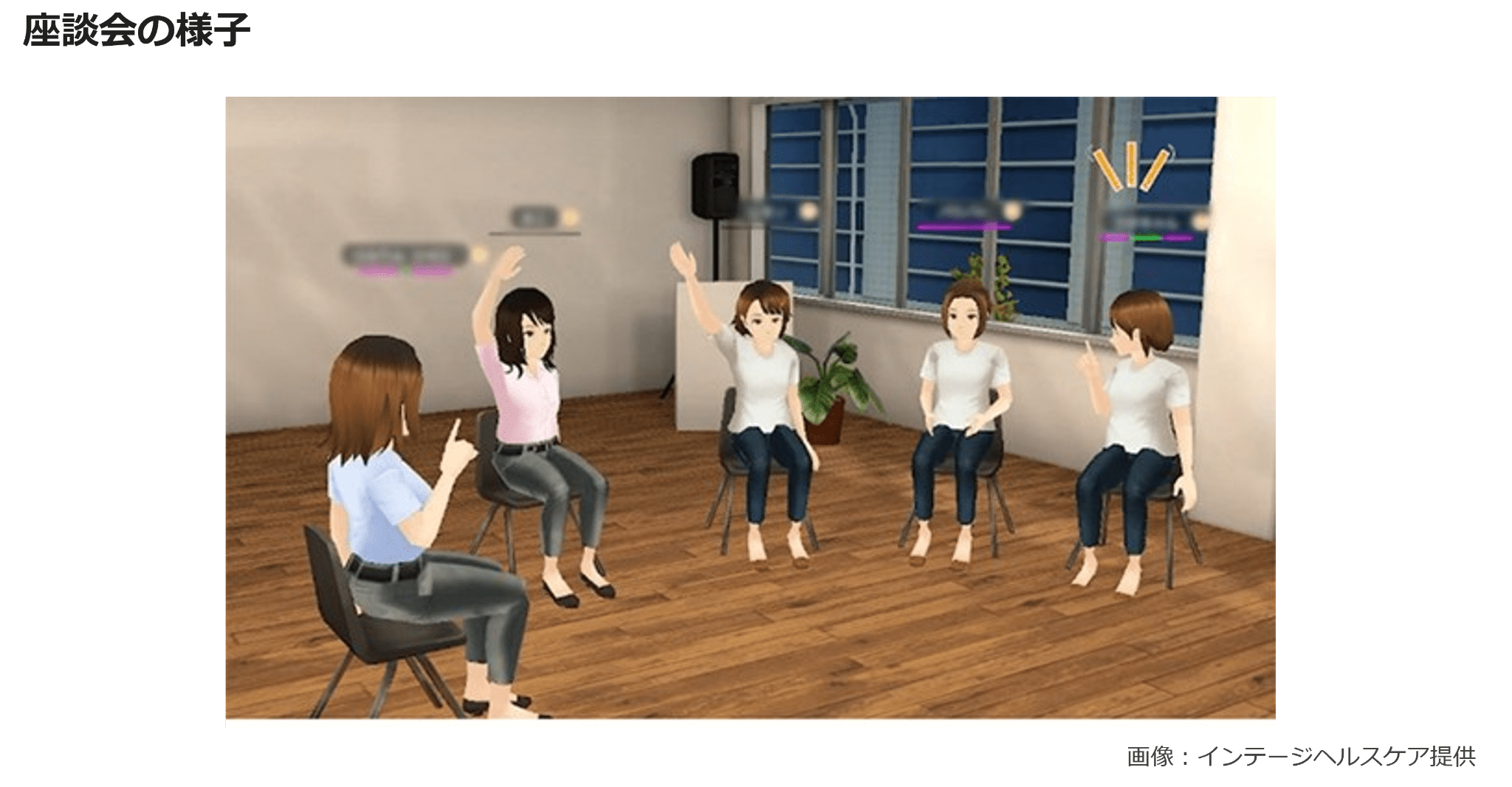
参加者が自身の顔を現すことなく、アバターを通じて意見を述べたり意思表示したりできることが、メタバース座談会の大きな特徴の一つといえます。それを裏付けるように、本実験の参加者からは「病気はかなりプライベートなこと。アバターを使って話せたので、安心して気持ちをさらけ出せた」「顔を出さなくてよいので、自分の疾患について率直に深い話ができてよかった」「ほかの参加者がアバターでリアクションを示してくれたので、安心して話すことができた」「アバターのキャラクターがすごくかわいいと感じた」といったポジティブな感想も寄せられました。
アバターの使用によって発言への心理的なハードルが下がったことがうかがわれ、またアバターのリアクションから互いの反応を可視化できたり、キャラクターに愛着を持てたりしたこともメタバース座談会の高い満足度につながったと推察されます。
一方、この取り組みからは、メタバースインタビューについて、以下のような課題も見えてきました。
まず、現時点では、参加者が限定されやすい点が挙げられます。具体的には、メタバースの操作に慣れていない年齢層や、デジタル機器の扱いに不安を感じる人々にとっては参加のハードルが高く、結果として比較的若年層やデジタルネイティブ層に偏る可能性があります。また、遠隔からの参加が前提となるため、通信環境によって接続が不安定になる場合もあり、通信遮断などのトラブルに備えた対応策を事前に検討・共有しておくことも重要です。
さらに、リアルの座談会をそのままメタバース上で再現するだけでは、メタバースの持つ特性を十分に活かしきれません。たとえば、仮想空間内を自由に移動できる特長を活かして、参加者同士が偶発的に出会い、対話が自然に生まれるような設計が求められます。加えて、「メタバース」という言葉に対するイメージや理解には個人差が大きいため、参加者の期待値を事前に丁寧に調整することも、円滑な実施のためには欠かせません。
こうした課題を踏まえながら、メタバース座談会ならではの設計や運営方法を模索していくことが、今後の活用拡大に向けた鍵となりそうです。
前章の取り組みでは、対象者はVRヘッドセットを装着せずにメタバース座談会を行いましたが、その後、インテージホールディングスの「メタバース分科会」では、インテージグループ社員を対象に、VRヘッドセットを装着してのメタバース座談会も実施しました。
この取り組みでは、対象者はメタバース空間でVRヘッドセットを装着し、モデレーターの案内に従いつつ、アバター同士が向き合う形式でグループインタビューを試行しました。2グループで実施し、参加者は各4名、合計8名でした。
この環境では、参加者はパソコンの前から画面上のキャラクターを動かすのではなく、みずからが3D空間の中に入り、他の参加者が目の前にいるかのような視点で会話ができます。
その結果、従来のオンライン会議システムを利用するケースより発言が途切れにくく、参加者同士の掛け合いや相づちが自然に続くなど、議論の活性化が確認できました。
なお、前章のVRヘッドセットなしの事例では、「モデレーターが質問して、参加者が答える」という状況が多く、参加者同士のコミュニケーションはほとんどありませんでした。一方、本章のVRヘッドセットありのケースでは、参加者同士でも、体の向きを相手に向ける、発言開始が被った際にお互いに譲り合うなど、リアルとほぼ同じような自然な動きで振る舞う様子が、多数観察されました。
また、この環境下では、参加者から以下のような感想も聴かれました。
「会話するときに必要な情報が口の動きや手の動きで補完されている。詳しい表情が分からなくても会話が成り立つし、雰囲気が分かる。」
「周りの人の体の動きや顔の向きを把握しやすい。また、音声が相手のいるところからちゃんと聞こえてくる。それらがあいまって、場の状況を把握しやすかった。」
ヘッドセットを装着した状況が、より現実に近い、没入感の高い環境と感じられたことがうかがえます。
この検証では「漢方薬の利用」をテーマとしました。顔を出さずに参加でき、VR機材利用によって議論が活性化したり、心理的ハードルが下がることから、医療や金融などセンシティブなテーマでも率直な意見を引き出しやすいことが予測されます。この点は大きな魅力といえるでしょう。距離や時差の制約を受けにくく、海外と同時に調査しやすいことや、仮想空間を自由に設計できるため、開業前の実店舗やサービスカウンターといった、現実では再現しづらい状況を用意できるなど、空間設計による拡張性の高さもこの手法の魅力といえます。
一方、この取り組みで、メタバースインタビュー運営面の新たな課題も浮上しました。現時点で、VRヘッドセットの装着を前提とする調査の場合、それらの機材に不慣れな層の参加ハードルが上がる点は否めません。また、VRヘッドセットの準備と接続テストには時間とコストがかかるため、慣れない操作に戸惑う参加者へのサポートも欠かせません。この検証でも、通信が途絶して議論が中断するケースがありました。長時間の着用では参加者がVR酔いを訴えるケースも想定されます。
また、VRヘッドセットの有無にかかわらず、参加者がアバターになると、顔の表情からの情報の読み取りが難しくなるため、従来のインタビューに慣れたモデレーターには新たなファシリテーションスキルが必要となります。
総じて、VRメタバースでのインタビューは「議論を深く広げる」という大きな可能性を持つ一方で、「技術と運営の壁」をいかに下げるかが普及の鍵となります。まだ検証人数が少ないこともあり、インテージグループとしても、引き続き検証を続けていきたいと考えています。
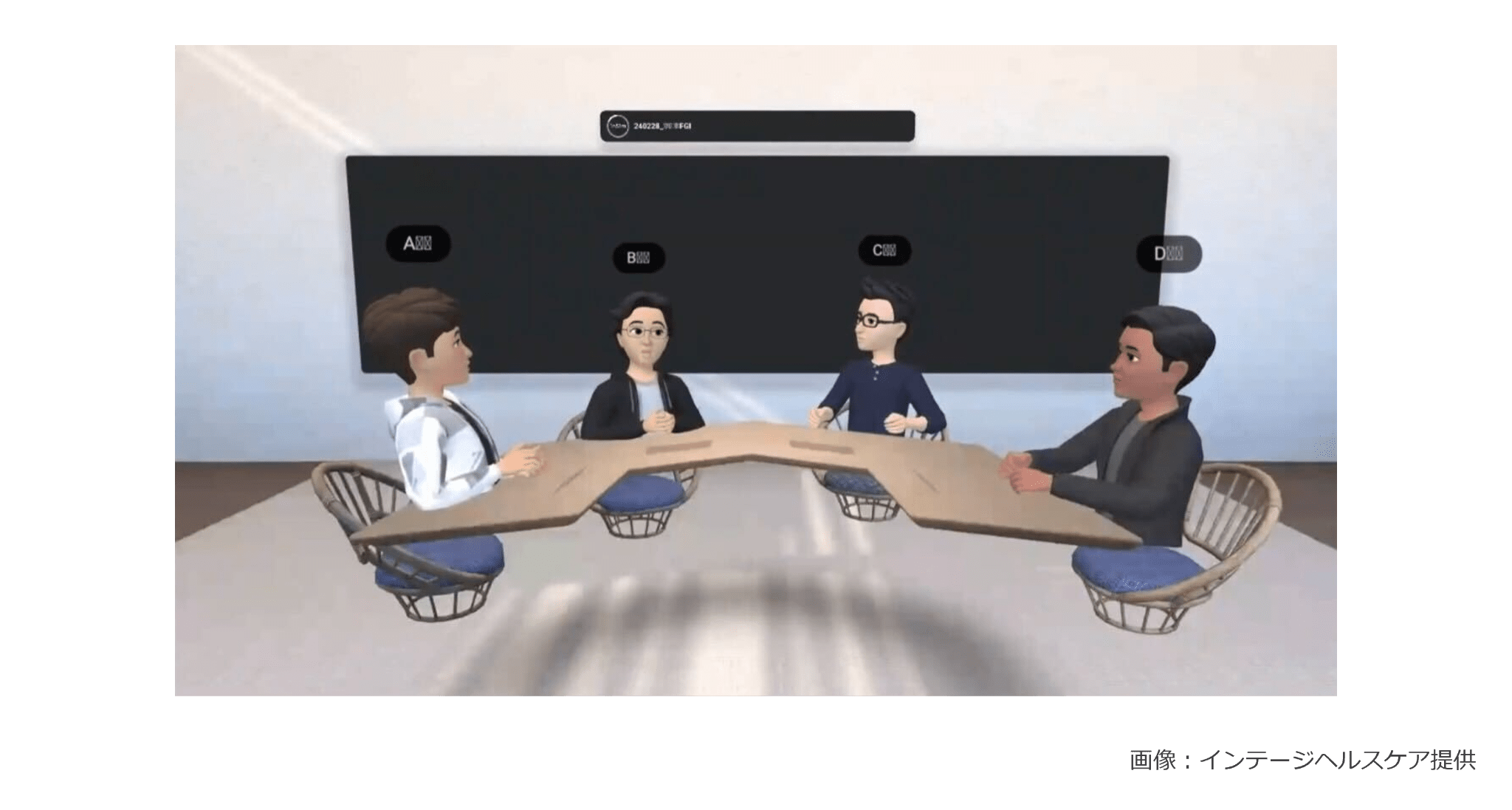
このように、メタバースにおける調査は、メタバース利用ならではの可能性も垣間見られるものの、様々な実施上の課題もあり、まだ発展途上といえます。今後の計測方法や分析方法、実査運用ノウハウの蓄積が求められます。
インテージグループでは、今後もメタバース空間におけるマーケティングリサーチの研究や、ビジネス応用に向けたサービス開発の検討を継続的に進めてまいります。
このような活動を活性化すべく、インテージホールディングス グループR&Dセンターでは、「XR/メタバース分科会」を設置し、メタバースを活用したリサーチの可能性について体系的な研究や知見の蓄積を行っています。
この分科会には、日常的にメタバースに触れているヘビーユーザーのメンバーが在籍しており、仮想空間の中で起きている文化やユーザー行動への深い理解をもとに、実務的なアドバイスや支援が可能です。また、インテージホールディングスは一般社団法人Metaverse Japanをはじめとする業界団体にも加盟し、業界全体の発展に向けた積極的な情報発信やネットワーキングにも取り組んでいます。
インテージグループのインサイト分析力と豊富な人脈を活かし、メタバースに関わる企業や自治体、クリエイター、ユーザーといった多様なステークホルダーがともに成長できる持続可能なエコシステムの構築に貢献することを目指しています。
本コラムが皆さまの次の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
メタバースとマーケティングリサーチ【前編】~メタバースの現状と、マーケティングへの活用可能性
◆本レポートの著作権は、株式会社インテージが保有します。
下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記ください 。
「出典:インテージ「知るギャラリー」●年●月●日公開記事」
◆禁止事項:
・内容の一部または全部の改変
・内容の一部または全部の販売・出版
・公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用
・企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的としたパネルデータ(*)の転載・引用
(*パネルデータ:「SRI+」「SCI」「SLI」「キッチンダイアリー」「Car-kit」「MAT-kit」「Media Gauge」「i-SSP」など)
◆その他注意点:
・本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません
・この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません
◆転載・引用についてのお問い合わせはこちら